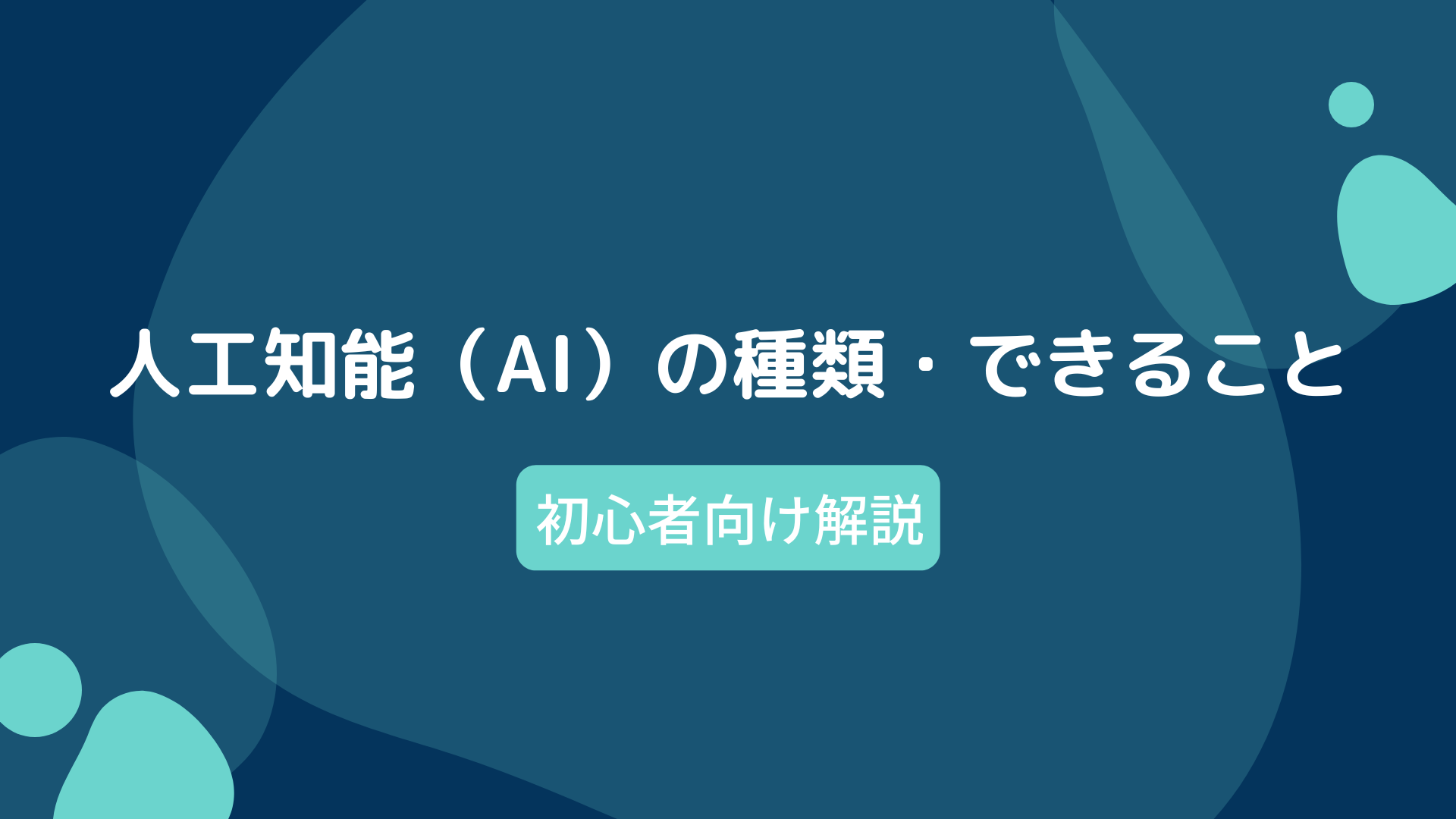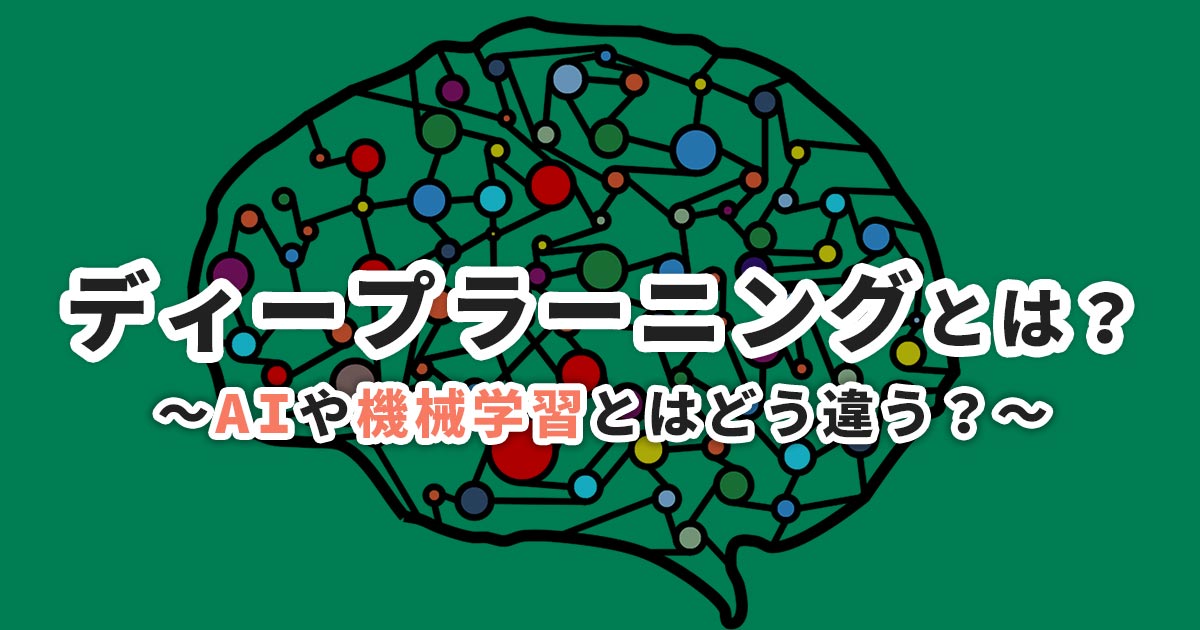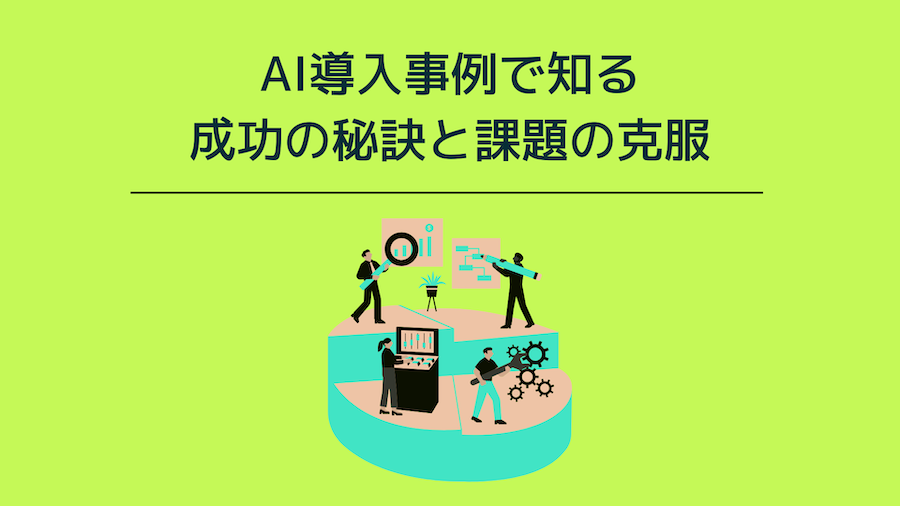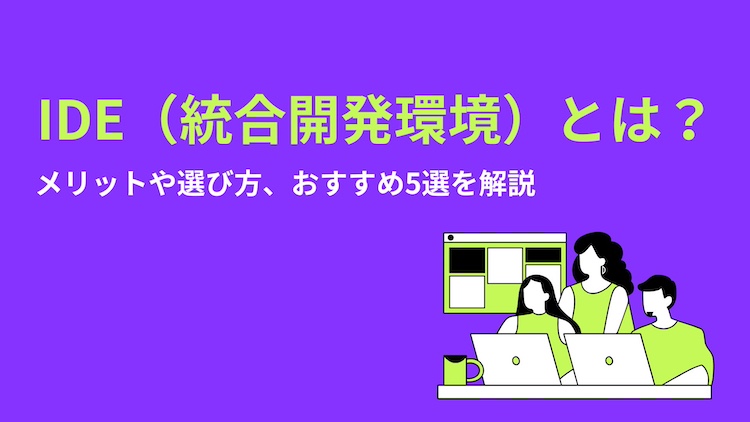- ITインフラ・システム開発
- DX支援開発(AI、IoT、5G)
使えるRAGの条件‑‑“つないだだけRAG”を卒業し、現場で成果を出すための設計・評価・運用
- [更新日]2025/11/13
- [公開日]2025/11/10
- 243 view
- Cognisant合同会社
使えるRAGの条件──“つないだだけRAG”を卒業し、現場で成果を出すための設計・評価・運用
はじめに:なぜ“使えないRAG”が量産されるのか
RAG(Retrieval‑Augmented Generation)は、大規模言語モデルに外部知識を結び付ける強力な手法です。しかし流行に乗って型どおりに組み合わせただけのシステムでは、現場で使える品質を得られません。未整備データの投入、検索設計の欠如、評価・運用設計の不足といった欠陥が重なると、答えは一見もっともらしくても根拠を提示できず再現性もありません。RAGを本番運用に耐える仕組みにするには、設計・評価・運用を分解し、各段階で意思決定と改善の基準を明示することが欠かせません。RAG評価では、検索や生成の性能に加えてコストやレイテンシを含めた三つの軸で測定する必要があり、Recall@kやPrecision@k、MRRやF1 などの指標を使って各段階を評価します。
第1章:RAGの誤解と限界を正しく掴む
RAGは「外部の知識ベースから情報を取得し、その情報を元に生成する」手法です。Retrieval がユーザー質問に関連するドキュメントをベクトル検索で引き出し、それを生成モデルが回答に反映することで、従来の言語モデルが抱える“幻覚”や事実誤りを抑えます。2020年に提案されて以来、特定領域の情報や最新情報を必要とするタスクで優れた性能を示すことが報告されています。しかしRAGは万能ではなく、厳密な計算や未整備の情報、権限や規約を越える取得には適しません。また、RAGの品質は取得した情報の範囲と精度に依存するため、検索が不十分だと生成も当て推量になります。適用範囲と限界を明確にし、RAG単体ではなくルールベースやデータベースなど他手法と組み合わせることが重要です。
第2章:使えるRAGの4レイヤー設計
使えるRAGには「情報設計」「検索設計」「生成設計」「運用設計」という四つの責務分割が必要です。
・情報設計:元のドキュメントをチャンクに分割し、メタデータや権限・更新頻度を整理して索引を作ります。日本語環境では表記揺れや固有名詞対策が重要です。
・検索設計:BM25 と密ベクトルのハイブリッド検索に再ランキングを組み合わせ、クエリの書き換え(Rewrite)や類義語辞書を活用して回収漏れを減らします。適切な類似度閾値と検索件数の調整が品質と効率の両立に直結します。
・生成設計:プロンプトの枠組み、引用の整形、出力形式、失敗時のフォールバック(テンプレートやルール処理)を定義します。引用元をリンクで表示するなど、ユーザーに根拠を提示するUIも設計に含まれます。
・運用設計:監視とアノテーション運用、A/B テスト、コスト・遅延のSLO管理を実装し、ログから改善のサイクルを回します。人手介在(HITL)を組み込んだアノテーション運用により高品質な評価データを蓄積し、モデルの改善に繋げます。
第3章:判断ポイントの実務基準
各レイヤーでどこまで整備できているかを評価するチェックリストを用意すると、自社の成熟度が可視化できます。主なポイントは次の通りです。
・データ成熟度:量・質・鮮度・権限境界を区別し、索引前に正規化や語彙統一を行います。
・検索手法の選定:文書長・語彙特性・構造化度に応じてハイブリッド検索を採用し、再ランクやクエリRewriteを組み合わせます。RAGの評価では、Recall@kやPrecision@k、MRR など情報検索の指標が利用されます。F1 スコア、BLEU・ROUGE なども用いられます。
・クエリ処理:正規化、Rewrite、明示スロット化を行い、曖昧入力や同義語による揺れを抑えます。
・評価設計:情報検索の指標(nDCG、MRR、Recall@k など)と生成品質の指標(Faithfulness、Groundedness、回答の関連度・流暢さ)を二層で評価します。定期的な評価は、ハルシネーションを減らしユーザーの信頼を高め、改善サイクルを速める効果があります。
・速度・コスト最適化:キャッシュ、前計算、近似探索、索引分割などでレイテンシと費用を抑えます。RAG評価ではレイテンシやコストも重要な軸の一つです。
・ガバナンス:権限付与や個人情報保護、監査ログ、アラート閾値の設定など、運用上の責任範囲を明確にします。運用SLOを設定し、逸脱時に通知やフェイルセーフを発動する仕組みを構築します。
第4章:標準ワークフロー
高品質なRAGを再現するための標準フローを定義すると、プロジェクトごとに失敗パターンを避けやすくなります。基本的なステップは以下の通りです。
1. 収集・整備:必要な文書を収集し、形式統一やメタデータ付与、権限整理を行います。
2. 索引:チャンク化した文書をベクトル化し、BM25 インデックスやベクトルデータベースに登録します。
3. 検索:ユーザーの質問を埋め込みに変換し、ベクトル検索とBM25 検索で関連文書を取得、必要に応じて再ランキングします。
4. 生成:取得した文書と質問を元に、プロンプトテンプレートに従って回答を生成します。引用文には出典リンクを付けます。
5. 検証:自動・人手の両方で生成物を評価します。情報検索指標や生成品質指標、業務KPIを計測し、基準未満なら再度設計を見直します。
6. 監視:運用中はログを記録し、SLO 逸脱やハルシネーション発生時はフォールバック(ルールベース回答やテンプレ)に切り替えます。変更管理を行い、小さな改修を迅速に検証します。
第5章:ケーススタディ(弊社対応過去実績)
・商社向け営業支援:メールから問い合わせ内容と条件を抽出し、社内在庫や価格条件を検索して提案素案を自動生成。人のレビューを経て学習ループに取り込むことで、初稿の品質と作成速度が大幅に向上しました。
・財務管理SaaS:FAQ や規約をRAG化し、数式検証や制約充足チェックを併走させたチャットボットを構築。根拠提示や計算結果の検証を徹底することで、問い合わせ対応時間を短縮し、回答の信頼性を高めました。
・広告プラットフォーム:営業メールをRAGで解析し、配信条件の検索と見積もり作成を自動化。提案書のテンプレート化とABテスト運用により、提案精度が向上し、KPI に基づいた改善が迅速に進みました。
各ケースに共通するのは、根拠表示とUI設計が利用現場の受容性を高め、人手を巻き込んだ学習ループが品質を押し上げたことです。
第6章:導入ロードマップ
RAGの導入は「PoC→MVP→Rollout」の段階でリスクを抑えながら進めます。
1. PoC(概念実証):仮説が成り立つかを検証する段階。明確な合否条件(必要な正答率や再現率など)を事前に設定し、小規模データで実験します。
2. MVP(最小実用製品):PoCで有望性が確認されたら、正答率・レイテンシ・コストなどのSLOを置き、アノテーション運用や評価自動化を導入して本番環境に近い形で運用します。
3. Rollout(本番展開):権限境界・監査・変更管理を整えつつスケールアウト。段階ごとに中止・継続の判断基準を明記し、投資の透明性と安全性を確保します。
第7章:現場への適用手順
5つのチェックリストで現状を点検し、最小構成から段階的にスケールさせます。
・データ:更新頻度や権限境界を索引に反映し、メタデータを業務語で正規化しているか。
・検索:BM25と密ベクトルのハイブリッドを試験済みか/再ランク手法やクエリRewriteのルールは明文化されているか。
・生成:引用の根拠リンクをUIで常時表示し、失敗時のルールやテンプレートを定義しているか。
・評価:オフラインのIR指標とオンラインのタスクKPIを結びつけ、回帰テスト用セットを持っているか。Precision・Recall・Groundedness・Faithfulness・回答関連度・流暢さなど複数指標を組み合わせると全体像が見えます。
・運用:ログから改善へのループが定期的に回っているか/SLO(正答率・遅延・コスト)のアラート閾値を設定し、逸脱時にフォールバックやアノテーション運用が発動する仕組みがあるか。
結び:Cognisantが担う役割と次アクション
RAGで成果を出すには、設計・評価・運用を任せきりにせず、責務を分けて計測と改善を回すことが必要です。本記事で紹介した四つのレイヤー設計と標準ワークフローは、RAGシステムをPoC止まりにさせないためのガイドラインです。Cognisantは、要件整理から設計・実装・運用改善までを一貫して伴走し、人手を組み込んだ評価・学習プロセスを構築します。次の一歩として、診断ワークショップで現状と合否基準を言語化し、小さなPoCでKPI に照らして検証することをおすすめします。RAG導入をご検討の際は、お気軽にご相談ください。
ご相談はこちらから
企画や要件が固まっていないご相談でも
お気軽にお問い合わせください。
-
01
相談する
-
02
要件ヒアリング
-
03
専門企業のご紹介
-
04
企業との
ご面談&見積取得 -
05
企業選定〜契約締結
サポート -
06
専門企業と直接
プロジェクト進行
※ステップ5以降はご希望に応じて
サポートいたします。
本サイトは、reCAPTCHAとGoogleにより保護されています。(プライバシーポリシー・利用規約)
EDITOR PROFILE
Cognisant合同会社
工藤 大地
Cognisant合同会社は、現場の言葉をAI/システム仕様へ“翻訳”し、素早く価値提供まで導く開発・コンサル一体型の企業です。代表の工藤大地は明治大学の文系出身。国内大手マクロミルでマーケティングリサーチの新規開拓営業を経験し、多業界の市場構造・収益ポイント・購買ファネルに通じています。営業で培った傾聴・合意形成と、エンジニアとしての設計・実装を両立させ、「市場のKPI→要件→システム設計(AI/Web/業務アプリ)」を一気通貫で行います。非エンジニアにも伝わる言葉で要件を整理し、最小PoC(実証実験=小さく作って確かめる)→学習サイクルで確実に伸ばす進め方を徹底します。“作るための要件”ではなく“売上や効率に効く要件”に翻訳してから着手するため、導入リスクと無駄な開発コストを抑えます。
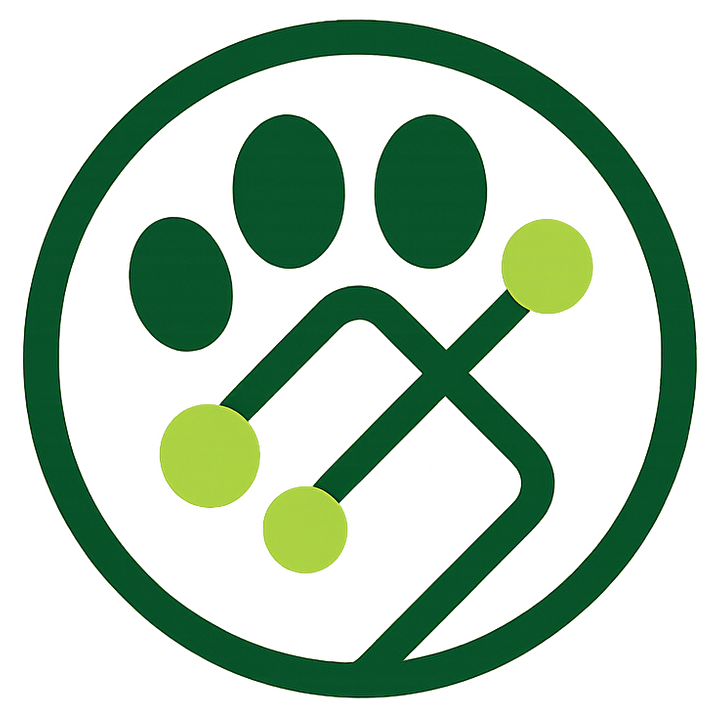
Cognisant合同会社
東京都
●オンライン中
DX支援開発(AI、IoT、5G)
WEBサービス開発
ソフトウェア・業務システム開発
他
Cognisant合同会社でできること
-
DX支援開発(AI、IoT、5G)
AI・IoT・5Gなど先端技術を活用したDX支援。企画から実装、内製化支援まで一貫してサポートし、業務変革を実現します。
-
WEBサービス開発
生成AIやRAGを活用したチャットボットや業務支援SaaSなど、要件定義からデザイン・開発・運用までワンストップで提供します。
-
ソフトウェア・業務システム開発
生成AIを組み込んだ業務アプリや管理システムを開発。迅速なPoCから本番運用まで対応し業務効率化と価値創出を実現します。
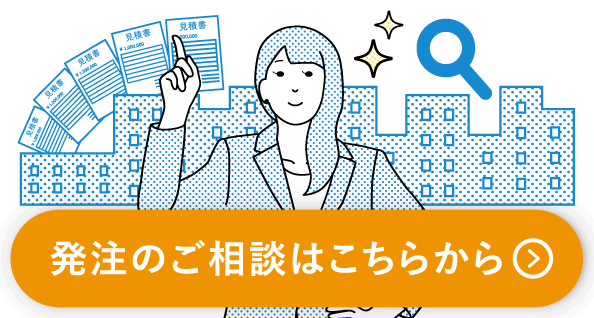
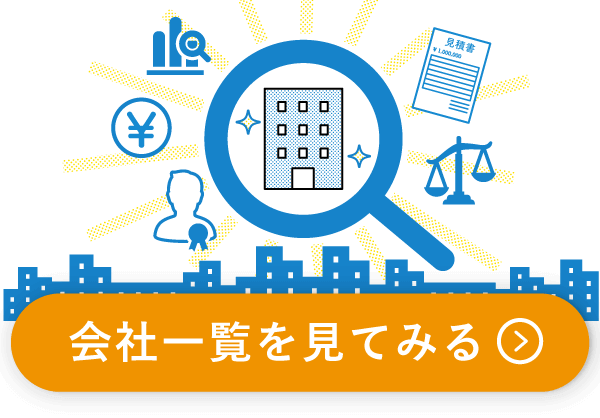
 シルバー
シルバー